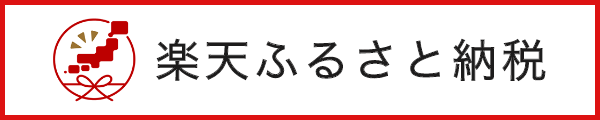鮎と日本文化
実は日本に現存する最古の書物「古事記」にも鮎を表現している記述があります。また、万葉集においては「年魚(あゆ)」と読ませ、特に佐賀県の松浦川や玉島川で鮎釣りをした様子などが詠われています。他にも俳句の季語として使われていますが、そのまま「鮎」や「鵜飼」は夏の季語として、春には「若鮎」、秋には「落ち鮎(産卵で川を下る様子から)」、冬には「氷魚(ひお・ひう)」と四季に合わせた活用がされています。
また、お供え物として捧げられた鮎は、日本の第14代天皇である仲哀天皇の皇后、神功皇后が釣りとをして楽しんでいたという記述もあります。皇室にも親しまれていたというのは素晴らしいことです。また鵜飼は平安時代から親しまれていましたが、この歴史自体も古いもので、日本の初代天皇である神武天皇の条に鵜飼部のことが記されています。鵜飼部とは、鵜を使って魚をとり、朝廷へ献上していた漁民のことです。鵜飼漁をする人のことを「鵜使い」「鵜匠(うしょう・うじょう)」と呼びますが、風折烏帽子、漁服、胸当て、腰蓑を身につけています。小舟でかがり火を焚き、この光に驚いた鮎が活発に動くことで、鵜に捕らえられます。あらかじめ鵜の首に紐を巻き付けているので一定の大きさ以上の鮎は飲み込むことができなくなっているので、鵜匠がそこを吐き出させて魚を得るのが鵜飼漁です。紐の巻き具合によって捕獲する鮎の大きさを決め、鵜匠ひとりで5羽から10羽の鵜を操ります。また、常に紐を巻いていると鵜はやる気を失ってしまうため、時折休暇を与えるなどの飼育管理も行います。現在は、船に乗って食事を楽しみながら、船越しに鵜飼を楽しむ催しものもあります。勢いよく上がる水しぶきや鵜匠の技はとても迫力があります。この鵜飼は、ヨーロッパにおいて16世紀末から17世紀頃にスポーツとして広まった事があります。鷹狩りと同じような貴族の遊びのひとつだったそうです。