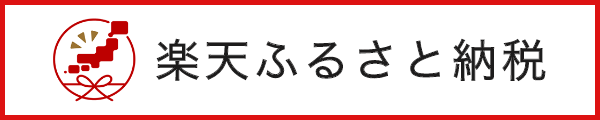養殖の歴史
鮎の養殖は、琵琶湖で1904年から石川千代松らによって行われたのがはじまりとされています。その後1960年代に、養殖用の稚魚を作るための活動が行われるようになり、琵琶湖産のアユが養殖種苗として使われました。養殖の鮎の生産量は1988年に最盛期を迎え、その後は減り続けています。
鮎の養殖
鮎の養殖の目的な2種類あり、食用になる鮎を育てる養殖と、川に放流するための種苗稚魚の養殖が日本各地で行われています。養殖するためのの生け簀は、長方形や円形などいろんな形状のものが利用されていて、水温は15度から25度に保たれています。エサは、魚の粉やすり身を主成分とした固形配合の飼料が使われることが多く、21世紀に入ってからは、動物質のエサの香りを抑えるためにさまざまな工夫がされています。養殖の鮎には特有の香りがないため、緑茶から抽出したエキスをエサに混ぜるなど、コケを食べて育つ天然の鮎の香りに近い養殖の鮎が育つようになったのです。最近では、ミカンの皮のエキスをエサに混ぜて食べさせることで柑橘類の風味を持つ「柑味鮎」や、ジンジャーやシナモンなどのハーブエキスを鮎に与えて、天然の鮎が放つスイカのような香りに近づけるなど、よりおいしく風味がいい養殖の鮎を作るための開発が盛んになっています。
養殖の苦労
養殖池は、屋根があるところもありますが外に設置されているため、気温の変化や大雨などの自然災害の打撃を受けやすく、浸水によって大きなダメージを受ける養殖場もあります。冷水病やビブリオ病など、鮎の感染症が発生する恐れもあるので、鮎の体調管理と水質管理にも気を配らないといけません。鮎の稚魚を成魚まで育てる過程で半分くらい死んでしまうので、鮎の様子を頻繁にチェックすることも必要です。鮎が育つためには新鮮な空気が不可欠で、空気を送るためのモーターのチェックもこまめに行い、もしモーターが動かなくなった場合は自家発電の機械を使って空気を送ることができるように対策をするなど、さまざまな気配りの元で養殖の鮎は育つのです。